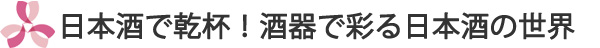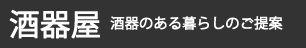小鹿田焼(おんたやき)

小鹿田焼(おんたやき)は、大分県日田市の北部の山あい、源栄町皿山を中心とする小鹿田地区で焼かれる陶器です。
江戸時代中期(1705年)に、筑前の国 小石原焼から陶工・柳瀬三右衛門を招き、大鶴村(現日田市)の黒木十兵衛によって開窯された李朝系登り窯です。民藝の器として知られる小鹿田焼は、柳宗悦が訪れ、バーナードリーチが滞在したとこりにより、知られるようになりました。
開窯以来300有余年にわたって、当時の技法を受け継ぎ、一子相伝で窯の火を守っています。 昭和32年3月、県の重要無形文化財となり、昭和45年3月には国の記録保存文化財の指定を受け、そして平成7年に国の重要無形文化財保持団体の指定を受けました。
小鹿田焼は現在10軒の窯がありますが、そのうちの5軒が共同窯に属しています。集落の真ん中にある共同窯は登り窯で、柳瀬朝夫窯、柳瀬晴夫窯、黒木富雄窯、黒木史人窯、坂本浩二窯の5つの窯が管理しています。
集落の中を川が流れ、その川の水を利用して陶土を砕く「唐臼」(からうす)が動かされ、時折唐臼が陶土を挽く音が聞こえてきます。その音は「日本の音風景100選」にも選ばれるほどです。
Youtube:唐臼のある風景