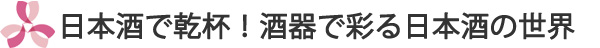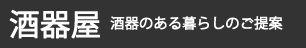有田焼

有田焼(ありたやき)は、九州の佐賀県有田町を中心に焼かれる磁器です。その積み出しが伊万里港からなされていたことにより、「伊万里(いまり)」とも呼ばれることもあります。
原料は、泉山陶石、天草陶石などを磁器の種類によって使い分けています。
作品は製造時期、様式などにより、
- 初期伊万里
- 古九谷様式
- 柿右衛門様式
- 金襴手(きんらんで)
- 鍋島様式 ※献上用の極上品のみ
- 禁裏様式 ※皇室に納められたもの
などに大別されます。
肥前磁器の焼造は、17世紀初期の1610年代から始まりました。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、肥前の領主であった鍋島直茂が日本に連れて来た陶工たちの一人の李参平は、1616年(元和2年)(1604年説あり)に有田東部の泉山で白磁鉱を発見し、近くの上白川に天狗谷窯を開き日本初の白磁を焼いたとされ、有田焼の祖といわれています。
有田は、江戸時代後期に各地で磁器生産が始まるまで、日本国内で唯一、長期にわたって磁器の生産を続けており、1977年(昭和52年)10月14日に経済産業大臣指定伝統工芸品に指定されました。